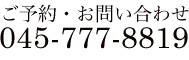1859年、横浜が開港された。欧州各国の西洋文化は長崎経由でオランダと中国から間接的に流入してはいたが、今度は直接5カ国分、しかも鎖国中の200年間分、新旧問わず同時に入って来た。貿易国は1869年までにはさらに11カ国増えたことで、16カ国の食文化が津波の様に押し寄せて来た。居留地には各国の公使館が建てられ自国から料理人が呼び寄せられ、料理や飲食風俗を伝える料理書が次々に刊行された。外国商社が自国の食料品を持込みホテルができた。本格的な肉食文化の到来はこれまで禁忌を解き放ち、直ちに和食文化と融合し、串焼き、コロッケ、カレーなどの屋台や、牛鍋屋、ビフテキ屋が生まれた。西洋野菜の栽培が本格的に始まった。フランス軍艦でパンの作り方を学んだ日本人がパン屋を開業し、カフェやアイスクリーム・サロンができた。
横浜の本格的なレストランを併設したオテル・ド・コロニーは、上海からたってきたフランス料理人のラプラス兄弟により1965年に開設された。ここでは築地ホテル館料理長に抜擢され、さらにグランド・ホテル・ヨコハマの初代料理長に就任、後にオリエンタル・ホテル・神戸を創業するルイ・ベギューが腕を振るっていた。もうひとりの横浜を代表するフランス料理人レオン・ミュラウールは、この頃フランス公使館の料理人として来日し、上野精養軒の料理指導役としても活躍した。
グランド・ホテル・ヨコハマは1873年、横浜の公共事業に尽くしたイギリス人スミス、写真家ベアドら数名が資金を出し合い設立された。そしてこの頃、居留地の洋菓子店では後の築地精養軒の初代料理長として招かれるスイス料理人カール・ヘスや、グランド・ホテル・ヨコハマの第3代料理長となるポーラン・ミュラウール、オランダ公使館では華族会館の初代料理長となり中央亭を創業する渡辺鎌吉や、鹿鳴館の初代料理長と鳴る藤田源吉が才能を開花させていた。1891年にはレオン・ミュラウールが、”横浜の華”と呼ばれたオリエンタル・パレス・ホテル・ヨコハマの礎を築いた。

明治になってまもなくの横浜は、1974年の外国船籍入港数は382隻。1877年の欧米商社167社、在横欧米人1,359人、輸出入品取扱高の実に全国比97%となっている。既に駅馬車や電信、鉄道が開通し、街にはガス灯が灯り、魚市場も開設されていた。水道供給は1887年から、電力供給は1890年からと、国際都市としてのインフラが整ってゆく時代であった。
グランド・ホテル・ヨコハマからはフランス外交官のお抱え料理人からイギリス公使館を経て東陽軒を創業する深沢為次郎、帝国ホテル初代料理長に就任する吉川兼吉、帝国ホテル第7代料理長の高木米次郎、帝国ホテル第8代料理長の石渡文治郎、ホテル・ニューオータニ初代料理長の小林作太郎らを輩出した。
オリエンタル・パレス・ホテル・ヨコハマからは、帝国ホテル第3代料理長のフランス料理人A.デュロン、帝国ホテル第4代料理長の後ホテル・ニューグランド・ヨコハマの初代料理長として招かれたサリー・ワイルの補佐役となる内海藤太郎、東陽軒さらに東京會舘初代料理長のA.プロジャン、築地精養軒第5代料理長の鈴木敏雄らを輩出している。また戦前から戦後と西洋料理界を牽引した荒田勇作は、グランド・ホテル・ヨコハマとオリエンタル・パレス・ホテル・ヨコハマの両方に在籍していた。
 オリエンタル・パレス・ホテル・ヨコハマ
オリエンタル・パレス・ホテル・ヨコハマ一流の西洋料理というと精養軒や帝国ホテルなど東京というイメージが強いが、料理人の辿った流れを整理すると、日本における西洋料理の源流となる溌剌とした横浜が見えて来る。横浜居留地を拠点に活躍し、精養軒や帝国ホテル、オリエンタル・ホテル・神戸などの料理指導をした、ルイ・ベギュー、ミュラウール兄弟、カール・ヘスの功績は大きい。
1897年8月19日と1903年1月1日から31日までのグランド・ホテル・ヨコハマのレストラン・メニューは、フランス語混じりの英語で、フランス料理には見られない何々風といった料理名や、各国特有の料理名の表記でタイピングされている。夕食、及び昼食ともにコースのみで総品目は各50種類前後である。スープ1種類、魚料理1種類、レリッシュ約13種類、アントレ約5種類、野菜料理約6種類、ロースト約3種類(昼食では冷製肉料理約6種類)、デザート約10種類、チーズ約5種類、それにコーヒーかお茶が付いて総品目は50種類前後が記されている。上から順番に選べるような構成になっている。アントナン・カレームの後を継いで19世紀のフランス料理を集大成したユルバン・デュボワがコース構成のロシア式サービスを広め始めたこの頃、横浜においてコース料理が提供されていたことには驚く。
日替わりのスープは、フランス料理の基本的なものの他に、クラム・チャウダーやチキン・ガンボといったアメリカの南北を代表する料理、マトン・ブロスなどのスコットランド名物料理、あるいはうきみにパスタやタピオカを浮かべた創作料理が見受けられる。また魚料理には、ロンドン名物のフライド・フィッシュやアメリカのオイスター・カクテルなどがある。さらにレリッシュには佃煮が定番として記されている。
アントレは今日のアントレ・シュクレという意味ではなく、文字通りの”間の手料理”として使われている。パスタ料理や米料理が多く、リゾット、ラビオリ、スパゲティーなどのイタリア料理、トルコ料理のピラフなどとバラエティーに富んでいる。特に鶏、羊、仔牛、鶏キモ、海老、牡蠣などを使ったカレーライスが日替わりで提供されていることから、人気メニューだったことが伺われる。
他には様々なイギリスのパイ料理。煮込料理にはアイリッシュ・シチュー、スペインのカジョスから創作されたと思われるスペイン風牛胃の煮込、アメリカのソウルフードになるデビルド・ピッグフィート、スニークなところではスッポン・シチューがある。またウェールズを代表するパン料理のウェルシュ・レアビット、日本の家庭料理となったハンバーグ、様々なコロッケ、ビーフ・シチューなども記されている。
コースのメインは、夕食はロースト、昼食は冷製肉料理で典型的なイギリス式であった。食材には鶏、豚、牛の他に、ジビエや内蔵が多く使われている。またアメリカの七面鳥も記されている。デザートはスコットランド名物のプディングが定番として記されている。
グランド・ホテル・ヨコハマでは、欧米各国の郷土料理が提供されており、当時の横浜居留地には、欧米各国、情報の新旧問わず同時に、かつ急激に西洋文化が流入したことが想像できる。さらに横浜で手に入る食材を巧みに使いこなし、欧米各国の食文化が複雑に組み合わされて、横浜特有の創作料理が生み出されていた。そしてこれらの西洋創作料理が、居留地に集まった日本人料理人に委ねられると同時に居留地の外に流出し、和洋折衷化された横浜創作料理が完成されたと考えられる。そして一般的に洋食と呼ばれるようになり、近代化の後押しの中、日本全国に広がっていった。
一方、レオン・ミュラウールが立ち上げたオリエンタル・パレス・ホテル・ヨコハマは、本格的なフランス料理を提供していた。魚料理には鯛や川マスなど、横浜で手に入る食材で工夫されている。肉料理にはリ・ド・ヴォーやモワル、田シギ、ブレス鶏、七面鳥なども記されている。驚くべき事にオーギュスト・エスコフィエが考案したピーチ・メルバや、牛フィレ肉のロッシーニ風を提供していることから、当時の横浜には最新のフランス料理があった。これまでエスコフィエの料理を日本で出したのは、リッツで修行した築地精養軒第4代料理長の西尾益吉であると言われていた。また遡って前身となったオリエンタル・ホテル・ヨコハマでは、1899年8月4日に行われた、安政5カ国条約改正の祝典晩餐会の記録が残っている。この晩餐会の料理は、パリのオテル・リッツやロンドンのサヴォイ・ホテルと同じレベルの料理構成になっており、ミュラウール兄弟の力量が知れる。
これらレストラン・メニューから、高級食料品の輸入もさかんに行われていたことがわかる。トリュフ、フォアグラ、肉類、各国のチーズやハムなど様々にのぼる。瓶詰技術、缶詰技術、冷蔵冷凍技術は1800年代初頭にはヨーロッパで発明されていた。ワインはシャトー・マルゴー、シャトー・ムートン・ロートシルト、クロ・ウージョ。シャンパーニュは実に20種以上。他にはカリフォルニア、ライン、キャンティ、トカイなど。リキュール、コニャック、ウィスキーなどの品揃えは今日のバーと変わらない。
1927年、関東大震災で失なった横浜文化を再建しようとする動きが起こりホテル・ニュー・グランド・ヨコハマが創設された。初代料理長はパリからスイス料理人サリー・ワイルを招き、補佐役に横浜の西洋料理界に深く関わった内海藤太郎、荒田勇作らを帝国ホテルから呼び戻した。厨房には、入江茂忠、山本政孝、戸村誠蔵、木沢武男、小野正吉、馬場久、水口多喜男らの腕に覚えのある料理人らが集結し、西洋料理の虎の穴と呼ばれた。ワイルは、グランド・ホテル・ヨコハマでコース料理として提供していた欧米各国の郷土料理を、日本で初めてアラカルト・スタイルで提供した。またこの厨房からドリア、ナポリタン、プリン・ア・ラ・モードが生まれたと言われる。
戦後の横浜は小さなアメリカだった。横浜の接収面積は、国内接収面積の62%にのぼり、市街地の返還は1961年まで待たねばなかった。通りや施設にはアメリカ名がつけられ、焼け残った建物は進駐軍クラブやシアター、PXになった。アメリカ料理が提供され、本物のジャズやブルースが流れていた。日本全体の社会体制が大きく作り直され、横浜では進駐軍の仕事を得ることはステータスとなっていた。そして接収が徐徐に解除されるにつれ庶民的な洋食屋やバーが沢山できていった。
1895年に横浜で生まれた荒田勇作が戦後集大成した「荒田西洋料理」には、100種類以上の米料理、200種類以上のパスタやピザを含む粉料理、米やパスタを工夫したタンバル料理が記されている。また戦前のグランド・ホテル・ヨコハマのレストラン・メニューに見られる、内蔵やジビエを使った料理も多い。横浜に流入した各国の料理が、どのようにして横浜創作料理となり、洋食としてアレンジされていったのか読み取れる。
横浜は諸外国と日本が交わる巨大なハブであった。横浜創作料理は、様々な人の手によって工夫され、姿を変えながら、新しい味わいとして受け入れられていった。その特徴は、各国の郷土料理を組み合わせる。手に入る新鮮な食材で工夫する。米やパスタで創作する。内蔵を上手く活かす。ジビエ料理などがある。「新しい星を発見するよりも、新しい料理を発見するほうが人間を幸せにする」そして「味わいの数は果てしない」。アンテルム・ブリア=サヴァランである。昨今の日本の料理人の活躍には目を見張る物がある。新しい料理は、今日も、明日も、世界中の街で生まれ続ける。パリでも、ニューヨークでも、そして横浜でも。
2015年10月5日
文責 ラトリエ1959 料理人 河内 暢也